生成AIが進化を遂げている。
エンジニアはもちろんのこと、公共の業務での利用もふえた。私たち一般人も、よく使用するようになり、もはや生活に欠かせないものになっている。
しかし、あまりにも判断をAIに任せっきりになってしまうのはどうなのだろう。危惧を覚える。
インターネット上のやりとりで諍いが起きた時、「AIにこの問題を判断してもらった。AIがあなたが悪いと言っている」という物言いをする人もいる。SNSなどでも、文章をChatGPTに任す人も多いという。
やすきの活用方法
やすきも生成AIを活用している。イメージを生成するMidjourneyと、DeepSeek。イラストに特化した派生型のnijijourneyで作成したイメージを、インスタのストーリーやBlogで、店の宣伝につかっている。
Deepseek(たまにclaude)では、料理のアイデア、音楽の情報を得ている。日本音楽メディアは、流行を追いかけるものしかなくなってしまって、やすきが追い求める情報がなくなってしまった。Newtone Recordなどのレコード屋の入荷情報や、noteの特定のジャンルに強い個人の記事で調べていた。
AIは音楽に詳しい。「サイケデリックでダビーなブラジリアン音楽のアルバムを教えてください。1970年代から1980年代のプライベートプレスで」と入力したら、意に沿ったものを提示してくれる。
エッセイも書いてもらって遊ぶこともある。雑誌POPEYE風にマニ教についての記事を書いて、と入力すれば、それっぽいものが出てくる。
やすきの場合は、自分の仕事での活用もあるが、楽しみながらつかっていることもある。
AIと仕事
AIが人間から仕事を奪う。危ぶまれていたいた事実は、意外にも創作の現場から始まっているようだった。
映画の脚本がChatGPTに書かれてしまうから、仕事を失った脚本家たちがハリウッドでデモを起こす。中国のゲームのイラストレーターの仕事が生成AIに取って変わられる。
2、3年前でさえ、クリエイティブの現場でこういうことが起きていた。
今後は、動画の生成AIが主流になっていくだろう。AIの性能が上がっていけば、個人の趣向に合わせた映画も数秒で作成し、楽しめる時代になってくる。そうなると、アニメーターや、映像関係の仕事もへっていくのだろうか。
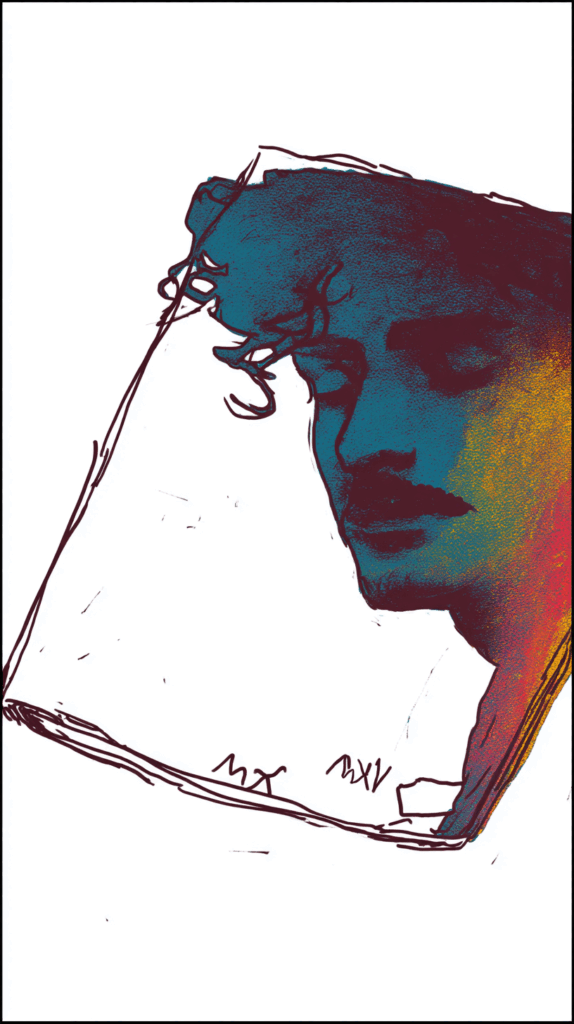
そうではないとおもう。
AIがつくる画像はAI特有の作風があって、見慣れた人だとすぐわかる。見慣れてないと、現実と見間違えてしまうものもある。
オリジナルなものを生成しようとすると、プロンプトを工夫する必要がある。作風にあたるもの。人間で言うと、個。癖。その人の特有の呼吸のようなもの。
みんなが排除しようとしているものが、より貴重になってくる。
AIは優等生というか、平均的な、ごく一般的なことを言う。AIによって均されていく地平線が、人間の個々の特徴という凸凹によって彩られる。
いままでは、個が和を乱すものともされてきたが、なにより大事なのだ。人間以外の知性が出現したとき、明らかになるのではないだろうか。
書に親しむ
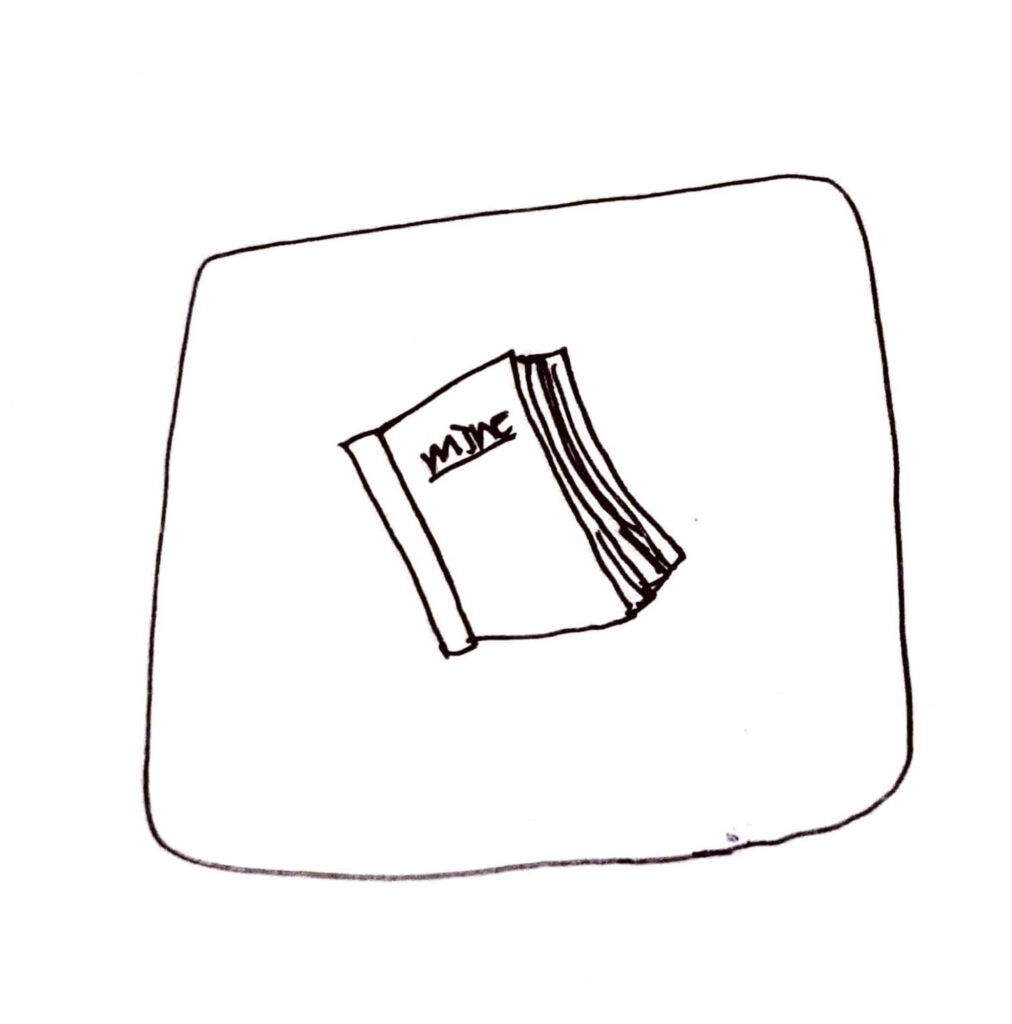
以前、文字に関する本を読んだことがある。アイヌなど、無文字文化では、文字がある文化より記憶力が高かった、という記述を見た。記録に脳が頼ってしまい、記憶力が減退してしまったのだろう。現代では、インターネットやスマホの出現によりさらに記憶力は低下しているだろう。検索すれば、ほとんどの知りたいことは知れる。
いちいちAIに聞いていては、さらに判断力、思考力も低下していくのではないか。パスカルは著書『パンセ』で「人間は考える葦」だと、思考力の偉大さを讃えている。デカルトのコギト・エルゴ・スムでもいいし、古今東西の哲学者がそう言っていて、現状を嘆くだろう。
SNSやAIで、瞬間の奴隷に化した人間。
どうすれば解放されるのか。
自分で考える、主導権を取り戻すためには、どうすればいいか。やすきは、読書を提案する。
効率の果て、自分の興味がある情報のみアクセスすることに慣れてしまったわたしたちに、読書は、遠回りも悪くないよ、と語りかける。
たとえば、小説。以前、hatisでカフカ会をしたことがある。フランツ=カフカの作品を、ワインを飲みながら討論し合うという集まりだった。
参加した十夢エリアマネージャーが、カフカを読んでも、どういう作品で、この本からどういう栄養を摂取すればわからない、というような事を言った。
カフカの作品はシュールというか、寓話のような、つかみどころのない形をしている。
やすきも、カフカの不思議な文体と、物語世界をたのしんでいただけで、作品に込められた教訓まで想いを巡らせてなかった。なぜ、カフカはこのような捉えどころのない作品群を書いていたのか。きっと、なにか伝えたいことがあったはずだ。
カフカは、プラハの民間保険会社アッシクラツィオーニ・ジェネラリで臨時社員として働き、その後、労働者災害保険局に転職した。短時間勤務ではあったものの、社会人として家族を養いながら、執筆にあたっていた。
浮世離れせず、実社会で働きながら、作品を綴っていた、ということになる。ならば、作品に、自分の生き様、教訓を込めていたはずだ。
ただ、自己啓発書のように、ここはこう、そこはそう、という風に明確な答えを書いていない。物語世界に入り、何を読み取るか、何を吸収するか。読む人次第で変わる。見えない土壌に、豊かな栄養が待っている。
その作品を、昔読んだときと、今読んだときでは、見方が変わる、という経験はだれしもあるだろう。優れた作品はそういう力を持っている。
やすきは、自分の生き方をしなければならなかったので、自らの考えや価値観を築いていく必要があり、読書がとても大切だった。書に親しむことで、自分に向き合う。本を一冊、部屋に置いておくということは、だれか1人と出会うことに等しい。そこから、自分が変わっていく。
受動的に情報を受け取るばかりでなく、読書をすることで、能動的な思考を取り戻し、AIを活用する方法を見出すことが、AIの時代を生きていく方法のひとつではないか。
こうやって、文章を書くこともそう。ひとつの記事を書くことによって、考えがまとまり、価値観が露わになる。自分の考えが明確になり、はっきりすることで、自分が好きになる。
普段、日時的につかうSNSも、アルゴリズムにAIが使われている。たとえばXでは、反対の政治意見をAIがタイムラインに表示することによって、リプからの論議が起きる。なぜAIがそんなことをするかというと、そうやってインプレッションを高めることによってX側が宣伝効果を上げ、利益を生むためだ。
YouTubeでも極端な意見な人が取り上げられてやすいのは同様の理由。しかも、そういった人の言うことをみんな信じ込んでしまうので、偏った物の見方の人が増えてしまう。
神道について、やすきは本で調べていた。スピリチュアルに詳しそうな人に出会った。その人はYouTubeから情報を得ていた。神道について話すと、本に書いてある学術的な知識と認識がズレていることに気づいた。
なぜこういうことが起きるのか。これも、十夢エリアマネージャーの意見だが、本は、出版元と著者がはっきりするので、責任が明確になる。それだけ、情報をしっかりしたものを伝えなければいけない。
一方、YouTubeはその場その場のエンターテイメントになっていることが多い。本もYouTubeも利益を前提につくられるが、プロフェッショナルの精度は出版業界の方が高い。歴史が深いからだ。YouTubeはここ10、20で勃興したプラットフォームだが、本は3000年からの歴史がある。
人は経験したことないなにかに出会したとき、自らの経験を参照にする。読書体験によって、視座をふやしておけば、役に立つ。内面も豊かになる。
最適化された選択肢を選ぶだけでなく、自らで考え、行動し、生き方を紡いでいく。本を読もう。人として、生きられるように。

