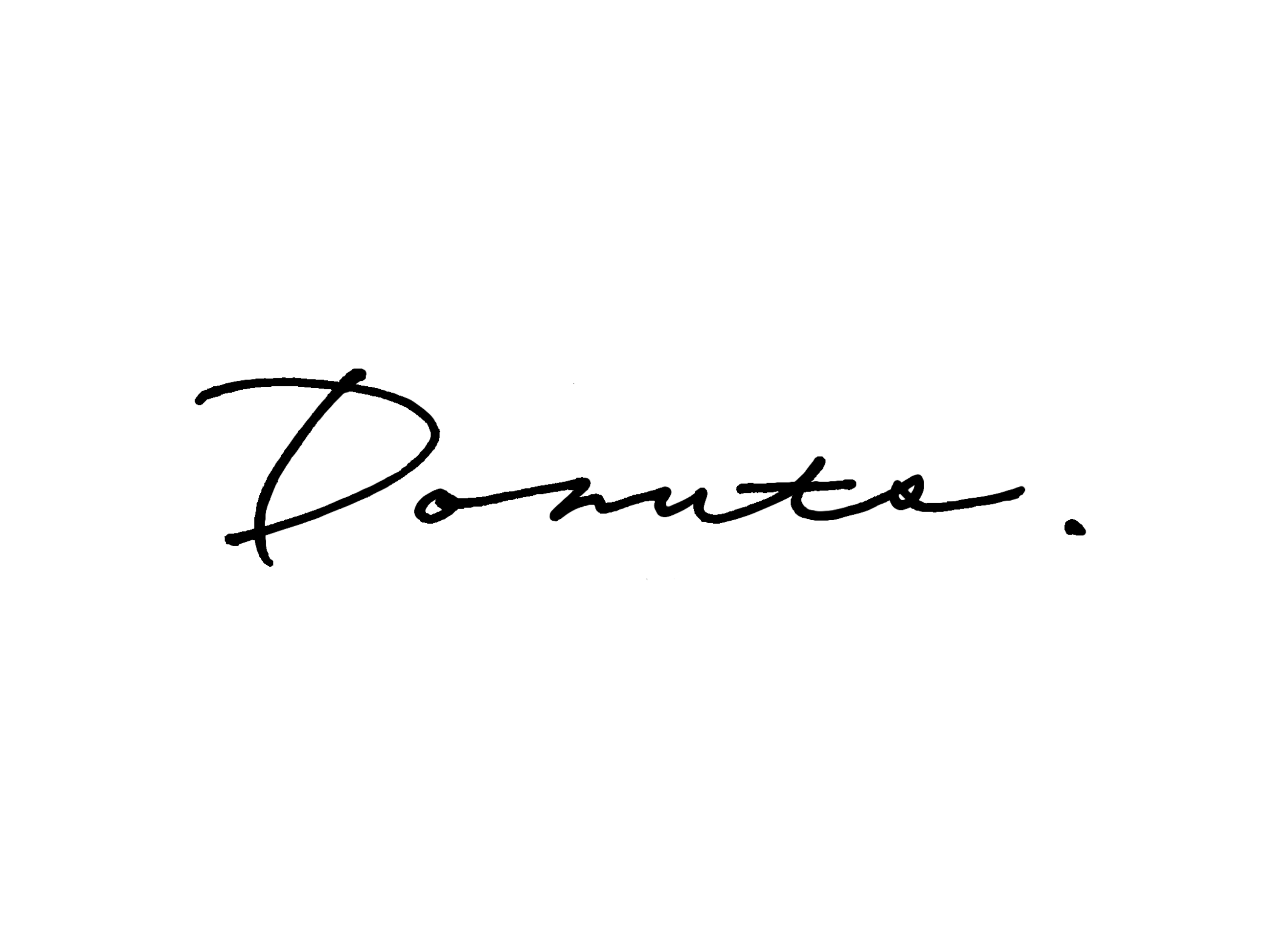私は約束した時刻より30分早く、〈Cafe du miconos〉に着いた。上町にあるカフェで、カウンターとテーブル席がいくつかある。
「よう、タケシ。」
約束した時間ちょうどに、その男は現れた。一分と違わなかった。私は彼を、ツッチーと呼んでいる。追浜の職場で知り合った。同僚はみんな彼をツッチーと呼んでいる。実のところ、苗字を知らないのだ。土田、あるいは土屋なのか、裏をかいて、津知さんなのかもしれない。
だが、私の知るツッチーは、そんなことがどうでもよくなるくらい、気風がいい男だった。身長は180cmくらい、細身の長身で、身なりも衛生的だった。仕事以外では、いつもVANSのスニーカーを履いている。年齢は一つ上。だれとも壁を作らないし、スマートな物言いが特徴。彼とは仲良しで、こうやって休日は横須賀で過ごしている。
「やあ、ツッチー、ご機嫌はどうだい。」
「ご機嫌もなにも、僕はいつもこの通りだよ。」
ツッチーは脇に紙袋を抱えていた。
「なにか買ったのかい。」
「ああ、そこの〈AMIS〉って古本屋に寄ってきたんだ。ヨソモノっていうZINEと、フランツ・オコナーの短編集を買った。」
「ふうん。」
「あそこのご主人は以前、東京の〈青山ブックセンター〉で働いていたらしい。だから、洋書が多いんだ。2、3ヶ月に一度、思い出したように行くんだが、顔を覚えてもらえない。その度に初めて会うかのように言葉を交わす。まるで違う世界で生き直して、再び出会うようにね。それを楽しんでるんだ」
「ふうん。」
ツッチーはよくしゃべる。私といる時だけ。その感じが楽しみで、彼と会っているのかもしれない。
「タケシはどうなの。」
「僕は、近頃の話題というと、買い物の場所を変えたね。いままでは、仕事終わりにリビン横須賀の〈西友〉に行っていた。休日に早起きするようになって、〈SANWA〉に朝イチで行くようになった。」
「ほう。」
「すると、気がついたことがある。いつも、開店と同時に4人くらいが走り出すんだ。ほとんどがおばあちゃんだ。そのうち1人は、とてもカラフルな帽子をかぶっていた。何をそんなに急ぐことが、と気になってついていったら、行き着いたのは半額コーナーだった。」
「なるほど。みんな朝イチで並んで、スーパーの半額商品をディグるわけだね。何が残っているんだい?」
「練り物。みんな、半額の練り物を求めて朝から走るんだ。中には、練り物でないものもある。こないだなどは、ご飯にかける冷や汁セットを買った。半額で100円だ。中身は、豆乳に湯葉が入っていて、納豆のタレのような小袋が入っている。うまかったが、たしかに200円では買わないような商品だった。」
「たしかに、それでは200円では買わないだろうね。」
「隣の〈AVE〉は、みんな魚の半額コーナーに飛びつく。こういった、開店前からスーパーに行列をつくり、走って半額コーナーに行く人を、僕はプロ市民と呼ぶ。」
「プロ市民。」
昼下がりの午後、時がゆっくり進む店内で、2人は珈琲を啜りながら、横須賀について話し合っていた。
ひとしきり話し合ったあと、平坂をくだり、横須賀中央の〈千里飯店〉で中華をたべた。私はエビチャーハン、ツッチーは名物の黒胡麻チャーハン。餃子を一皿たのんで、ふたりで分けた。この店は餃子が皮から手作りだ。モチモチしている。ある時間帯に店に入れば、威勢のいいおばちゃんがカウンターで餃子のタネを皮に包んでいる。
チャーハンをたべながら、私がいま、読んでいるマニ教についての本について話し合った。満足するまで話して、横須賀中央駅で別れた。夕方5時半だった。私は電車に乗らず、そのまま米が浜通りを歩いて安浦まで帰った。