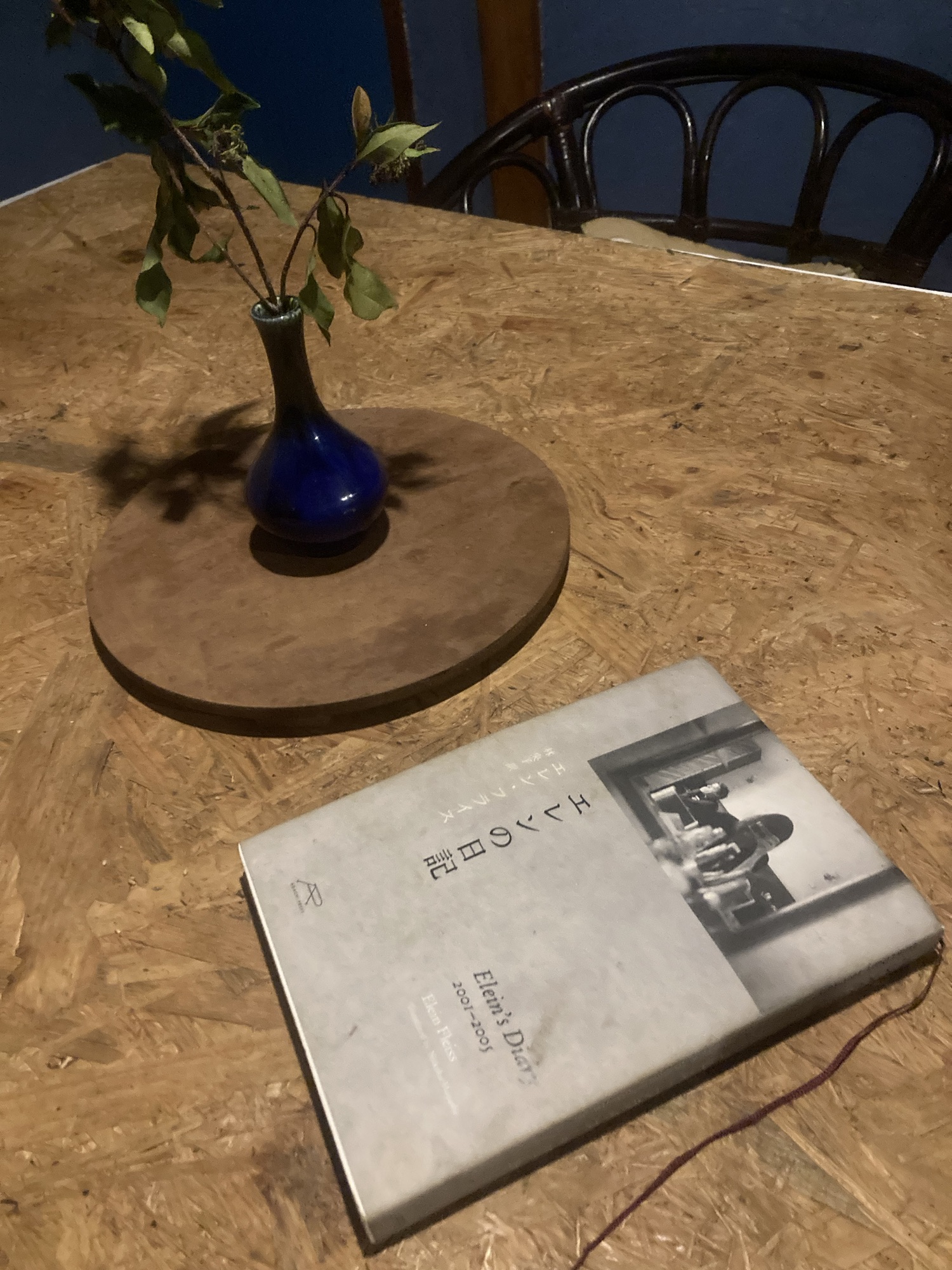エレンの日記
エレン=フライス / 林 央子 訳
青々と広がる瀬戸内海。しまなみ街道は、広島と四国を跨ぎ、つないでいる。サイクリングにも最適な場所として知られ、世界中から人が集まる。特に、ドイツ人が多い。ドイツ人は、アウトドアの遊びに熱を注ぐ。
しまなみ街道の起点となる広島県尾道市。古くから海運で栄えてきたこの街は、詩情の街でもあり、志賀直哉をはじめ、文豪が暮らしていたことで知られている。
散策してみると、街全体が物語に包まれているかのようだ。鎌倉に近いものがある。海があり、坂がある。やすきがかつて住んだ神戸にも地形的条件が似ていた。
街の中央部にある商店街に、〈あなごのねどこ〉という変わった名前のゲストハウスがある。まさに、巨大なあなごが住めそうな構造になっていて、入り口が狭く、奥が縦に長い。「うなぎのねどこ」ということわざをもじったものだろう。2018年、やすきは初めて尾道を訪れたとき、このゲストハウスに泊まった。
縦に長い通路を行き切ると、明るい庭が見えてくる。箱のような建物に、お店がぽつんとある。〈紙片〉だ。白昼夢のように美しい書店。「エレンの日記」は、この店の本棚からたまたま手に取った。
フランスのカウンターカルチャー
イントロダクションにはこう記してある。作者のエレン・フライスは、1968年生まれのおひつじ座の女性。
パリ近郊の街、ブローニュ=ビヤンククール出身。21歳で父親のギャラリーで企画した展示が評判を呼び、フランスのアートシーンに名が知られるようになる。
1992年、パートナーのオリヴィエ=ザームとともにアートのZINE「Purple Prose」を発刊。マドンナの写真集の発売日と同じ日だった。カップルを解消後も、彼女らは仕事を続け、次第にフランス、ヨーロッパ全体にも影響力を持つようになり、「Purple」と名を改めた。
オリヴィエは商業主義に走るようになり、編集方針の違いから、二人は決別することになるのだが、その変遷は、この本の中でも語られている。エレンは、「Purple」とは別に「The Purple Journal」を刊行することになる。
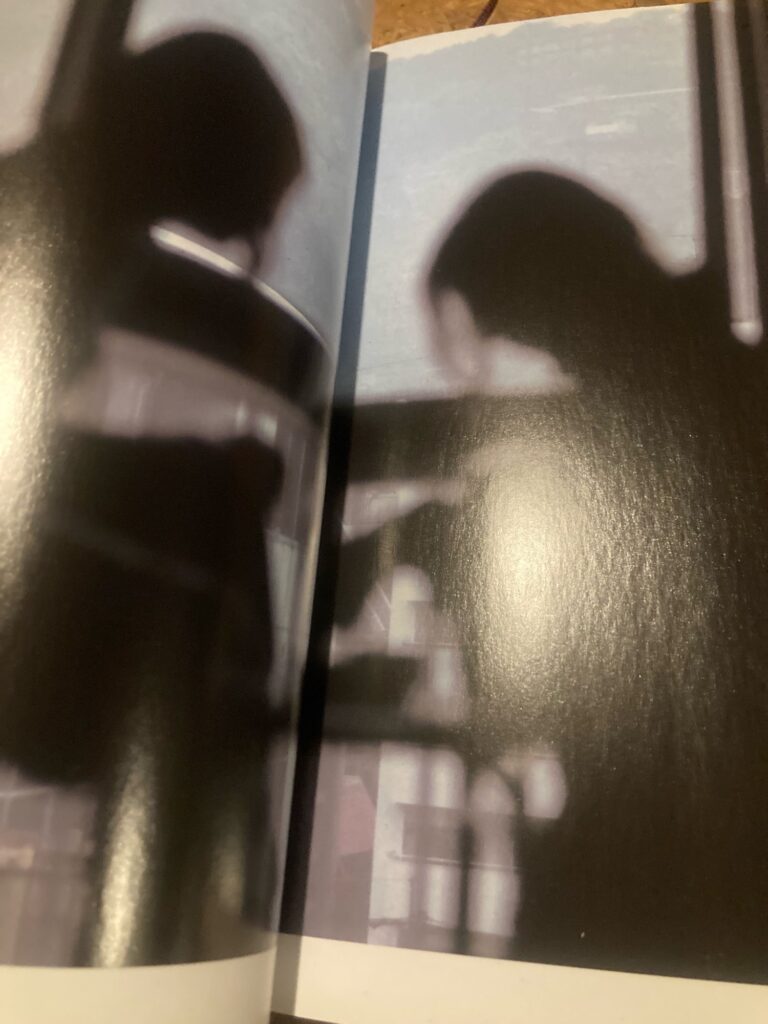
前情報もなく、突然にやすきはこの本を手に取った。イントロダクションを読んでも、ヨーロッパのファッションシーンのことなんて知らないやすきには、なんのことかさっぱりわからない。
90年代のパリが、カルチャーの発信から遅れていて、ロサンゼルス、東京、ロンドンは進んでいた。その比較線上に、X-Largeを発信していたビースティ・ボーイズの名前が出て、ああ、ようやく知っている単語が出てきた、と安堵したくらい。
みなさんも、本屋に行って、何気に本を手に取ったことはないだろうか。並んでいる本がちらっとこちらを見て、わたしはあなたに必要なんだよ、と目配せをしてくる。その直感はおおよそ当たっていて、読むと、自分に大きな影響を与えてくれる。
写真、ファッションなど、視覚面での表現に特化していた彼女は、この本のもとになった連載を書くことが、文章を書く初めての機会だったという。
確かに、序盤の文章は細切れで、辿々しく、文章に慣れていない様子が見て取れる。連載を重ねるにつれ、筆が乗ってきて、感情を直線的に表現する彼女の生き方が見て取れるようになる。好き嫌いがはっきりしていて、他媒体の悪口も平気で書いている。とは言っても、陰惨としてなくて、晴空のようにスカっとしている。「Purple」を発刊したのも、当時の雑誌のメインカルチャーに対する反発が理由で、怒りが彼女の大きな原動力だ。
ファッション、アート、音楽、旅、食、哲学、政治。業界の体質や確執に揉まれながらも、知を美を自由に楽しむ。彼女が好むアーティストの名前が、彼女の素地の広さを示しているだろう。ソニック=ユース、シュテファン=ツヴァイク、ニール=ヤング、楊乃文、クリス=マルケル、村岡久美子。彼女の友達の写真家、料理人、ヘアドレッサー、哲学家。
「エレンの日記」は、やすきの文筆へ、大きな影響を与えた。この本と須賀敦子の文体を足して2で割った文章を書きたいくらいだ。ドライで、インディペンデントで、淡々と物事を平坦に観察する様が、活き活きと伝わってくる。彼女は取材で、世界中の街を渡り歩く。パリ、リオデジャネイロ、アルメニア、ヴェネチア、コペンハーゲン、マドリード、鎌倉、長崎。
この記事を書くにあたって、初めて彼女のことをインターネットで検索してみたのだが、エレンは連載が終わった後、フランスからポルトガルへ、その後に南西仏の小さな村に移住したらしい。日本で言うと、東京から鎌倉に移住したようなものだろうか。この本の訳者である林央子さんとはプライヴェートでも付き合いがあり、日本も時折、訪れているようだ。
もし手に取られる機会があれば、ぜひ読んでみてください。