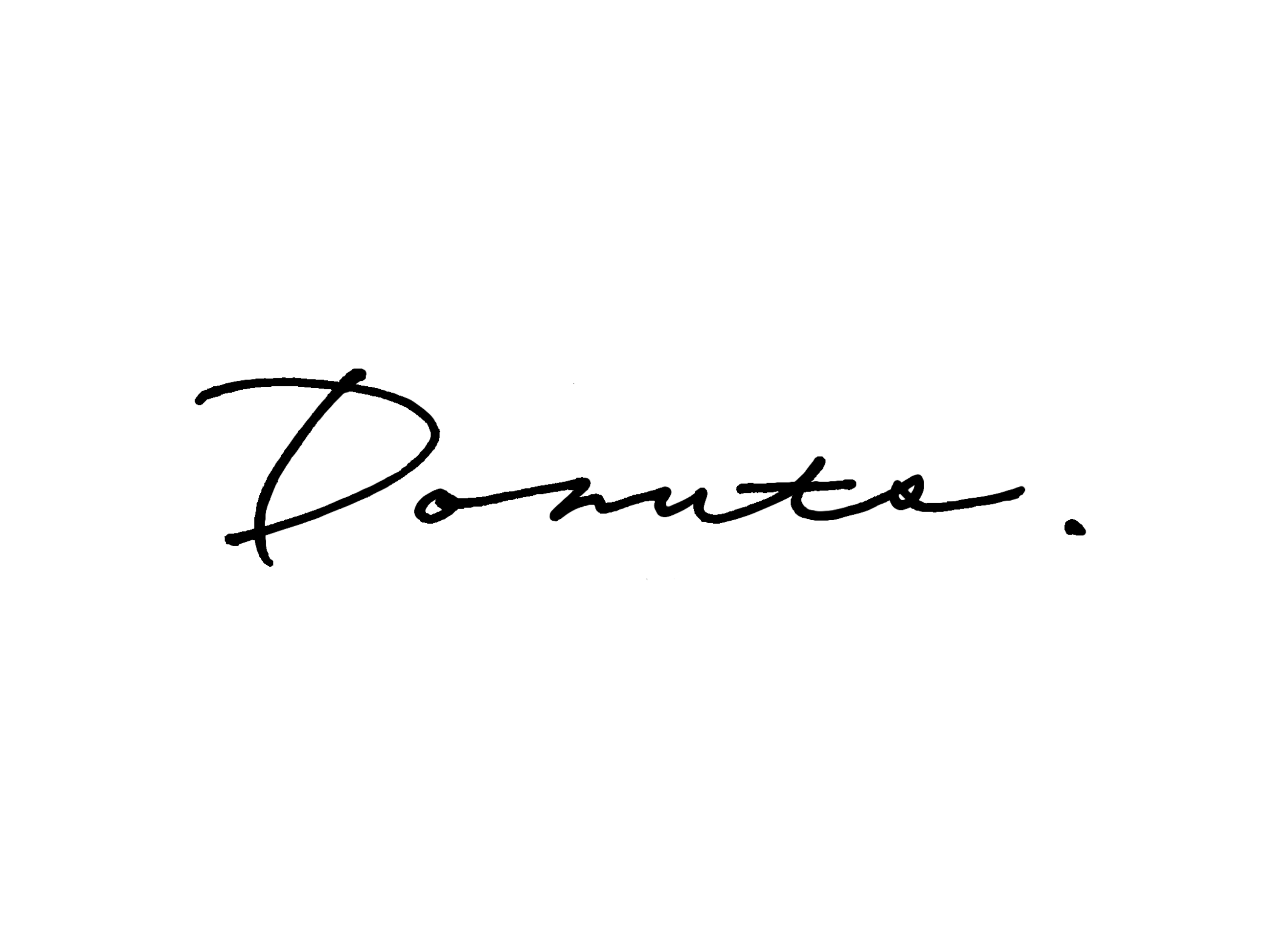追浜駅の北側には角打ちがある。角打ちとは酒屋さんのイートインで、もっぱら立ち飲みだ。総じて、安く飲める。
私の角打ちデビューは大阪だった。中津という、梅田の一本前の駅に、有名な角打ちがあって、大阪に住んでいる同級生たちとよく通ったものだった。
1杯200円か300円だかで、いろんな種類のお酒が飲める。冷蔵庫に入ってる酒のアテも、勝手に取って、後で精算される。ほとんどが500円以内だった。
仕事終わりに同級生たちと、まずここで飲み始め、酒代を安くあげるのがたのしみだった。中津は小さな面積にいい飲み屋が密集していて、いい街だった。
梅田の華やかさとは裏腹に、中津はおどろおどろしい雰囲気がある。こんな狭い道幅があるのか、という商店街の中に、JBLのスピーカーが設置されたお洒落な飲み屋がある。夜まで空いてる古本屋。私が尊敬しているスパイスカレー屋の〈soma〉。全てを飲み込んでしまうような、カオスティックな夜の街だった。空気が地元の津山にも似ていて、大好きだった。
地下アイドル

追浜も、似たような空気があるのかもしれない。工場地帯で、労働者の街。たまに、県立大学駅では見ないようないい身振りの人も歩いている。外国人労働者のいた名残か、駅前にはスパイス屋さんがある。
〈ぼちぼち書店〉という、素晴らしい名前の古本屋を見つけた。ウンベルト=エーコの「薔薇の名前」を見つけたが、下巻しかなかったので、ヘルマン=ヘッセの詩集を買い求めた。訳者が生前のヘッセと親交があったらしく、いい訳で、いい装丁の、いい本だった。
追浜本町の解体の仕事を5時に終え、駅に向かう。帰り道には、おとうふ屋さんや、〈はびき野〉さんという定食屋があった。入口には、カツ丼が450円という張り紙がしてあった。物価高の日本は、違う世界線の話のようだった。
〈安井商店〉さんに入る。中では、妙齢の女性かワンオペで回していた。10席以上ある店内に、なぜかカウンターが2つもある。女性はカウンターを行ったり来たりしていた。1つにしたほうがいいんじゃないだろうか。
カウンターには缶詰や焼き鳥、豆類が置いていた、ピーナッツはたしか60円だった。1杯330円のにごり酒とピーナッツを頼んだ。女性が席までグラスを持ってきてくれて、お酒をパンパンに入れてくれた。
先に済ませておこうと、「お手洗いはどこですか?」と聞いた。「そうだよね、知らないよね」と女性は答え、店を出て右側の細道にある厠の場所を私に告げる。その返答から、私のような新参者はイレギュラーであることを察した。
席について、にごり酒を飲み始まる。美味しい。肉体労働のあとの体に染みる。追浜の労働者の気分を追体験している気分になった。もはや、じっさいにそうか。
神奈川に移住して以来、お酒でアレルギーのような症状が出るようになったので、飲みに行くのが楽しみではなくなったが、日本酒は別だった。添加物の入っていない、いいお酒は身体が反応しない。
飲んでいる内に、人が集まってきた。仕事終わりにの人たちで、店内の席は、ほぼ満員になった。
中津の角打ちに通っていた頃と違うのは、コロナ以後だということ。中津では、お酒を片手にみんな明るく談笑していたが、今は、黙酒だ。席はプラスチックの板で仕切られ、みんな静かに飲みながらテレビを見ていた。
テレビでは、女子高生が男性地下アイドルに300万円を貢いだというニュースが流れていた。追浜と、かけ離れた東京の情景だった。それが本当にあった事実なのかさえわからない。
店を埋め尽くしている、50代から60代と見受けられる男性の客たちは、300円だかのお酒をのみながら無表情にこのニュースを眺めていた。
300万円を貢がれた地下アイドルに、何を想うのだろう。もしかしたら、何も想わずに情報を消費しているだけなのかもしれない。
テレビには次々に重要でないようなニュースがながれ、みんなそれを吸い込まれるように見ている。あまり話もせず、各々のお酒を飲み続ける。
古い棚にお酒が並んだ猥雑な空間に、ある種、異質な時間が流れていた。映画の中に入ったような気分だった。ジョージ=オーウェルの『1984』の世界に近かったのかもしれない。
地下アイドルのニュースも、コロナも、全てがウソで、工場で8時間働き、安酒を飲むという設定を楽しむ未来のBARだったらたのしいな、と想像した。
白昼夢

斜め右前の席に、背の高い白髪まじりのおっちゃんが卵を置いた。席に卵を置いてから、おっちゃんはカウンターに1度もどった。その間、卵が傾いて、床に落ちた。席に戻ってきたおっちゃんは、席に置いていたはずの卵がなくて驚いていた。その驚きの表情が、目を丸くして、俳優さんの演技のように鮮やかだった。
「卵、床に落ちましたよ」と思わず口にした。すると、おっちゃんはニコッと笑って床から卵を拾い上げた。卵は不思議と無傷だった。
おっちゃんは、カウンターから、大サイズのレモンサワーと、小さなサイズのステンレスボウルを持って帰ってきた。
いったいなに使うのかと気になって観察していた。おっちゃんは嬉しそうに卵を剥いて、殻をそこに捨て始めた。卵はゆで卵で、店の商品だった。
ゆで卵に塩を振り、レモンサワーを流し込む。いままでに見たことのない飲み方だった。白昼夢のような光景だった。
あまりに異質な光景が連続するので、もしかして、本当に違う世界線に入り込んでしまったのではないか、と考え出した。現実と異界の境目が、曖昧になりつづけている。
それはそれで仕方のないことだ、人生は選択の連続なのだから、と腑に落としこんで、300円の日本酒を追加した。群馬の酒だった。
店を出て、駅に向かった。中津の思い出も、いま飲んだお酒も、現実であることを祈りながら。