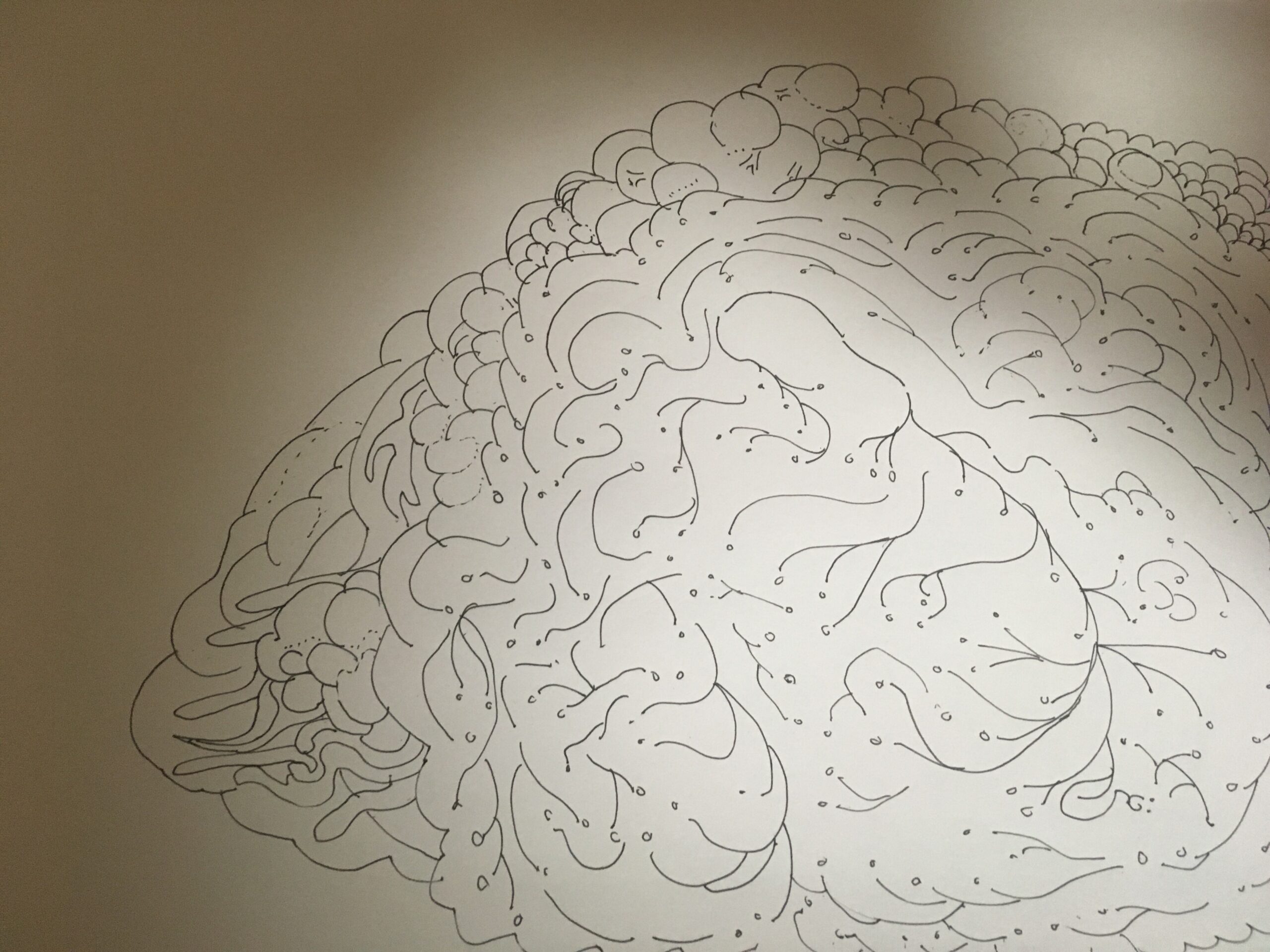最近、よく耳にする『インバウンドマーケティング』。一体どういうことなのだろうと、上の本を読んでみました。著者はマーケティングエンジン代表取締役兼共同創業者。マーケティングの第一人者です。信用できる本。
インバウンドマーケティングとは
インバウンドマーケティング」というのは、言ってみればマーケティングを行うときのマインドセット、即ち「態度•姿勢•考え方」そのものです。
Inboundを英和辞典で調べてみると内側から中心に向いた様、を表すようです。このウェブマガジンの今の所のように、いくら記事を書いたとしても多くの人には届きません。なぜなら、情報が膨大だからです。では、どうやってこのウェブマガジンにある記事を興味のある人に届けられるか?
テレビをはじめ、多くの情報が、多くの人にとってどうでもいいことです。知らない誰かの不倫のことなんて本来はどうでもいいことですから。
むしろブログに必要なのは、自分たちがつながりたい人びとがどのようなことに興味を持っているか、どのような課題を抱えているのかを把握した上で、それに関連するコンテンツを提供することです。
人びとは検索行動をする
いま、モノを買うにしてもどこかに行くにしてもほぼすべての人が一度検索をすると思います。何かを調べるとしたら、1日に10回はGoogleを使用するかもしれません。その時にhatisu8と繋がる可能性があります。その調べ物にこのウェブマガジンのコンテンツが引っかかれば見てもらえる。過去の記事も見てもらえる。
GoogleがZMOTという考え方を提唱しています。これはその商品と店頭で出会う前に、パソコンやスマホを通してその商品の情報と出会う、というもの。口コミレビューも含めて。あなたが欲しいと思ったレコードに、hatisu8のレビューが役立てば幸いです。その人が欲しいと思った他に、新しいモノ、価値観を提示できればもはやブレイクスルー。望外の喜びですね。
来訪者を惹きつける
これまでのマーケティングが「人びとはあっちを向いている」ということを前提にしていたのに対して、インバウンドマーケティングは「こちらを向いている人がいるはずだ」という前提に基づいていろいろ施策を打ちます。
そこで、何かを探してる人びとから「見つけられる(Get Found)ために、それらの人にとって「役に立つ(Useful)」コンテンツを提供して、サイト来訪を促すのです。
これをローカルに置き換えるとどうなるか


これをサイトではなく地方に置き換えるとどうでしょうか。現在、日本では毎年東京に9万の人がふえ、各地方から少しずつ人が減っています。一極集中しすぎなのです。ですので各地方は東京からデザイナーを招き、魅力的なコンテンツを作成しようとしています。東京の力を借りなければいけないのがなんとも皮肉ですが….。
地域を変えるソフトパワーという本の、滋賀県近江八幡市の近くにある、島町という農村の話が印象的でした。
島町は典型的な農村ですが、近江八幡の中心市街地から近く、職場や買い物も不便ではない。後継者問題もなく、生活に困らない。するとそこに何が起きるか、農村の都会化だというのです。隣人との交流がなくなるということ。その結果、文化が廃れていく。
私が住んでいる岡山県津山市というところもそうです。田舎ですが、ロフトもGUもありなにかしら困らない田舎。ですので、友人に話を聞くと、人に合わなくてもいいそうです。中学生の同級など、同じ町に住んでいてもまず合わないそう。
ここに問題があるのではないかと思いました。人口減少はどうしようもないとして、それではなにを失ったかというと地域のつながり。ネットでなんでも買えるから、人とのつながりがない。色んな人と繋がれるツールなのに。
瀬戸内海の島ではアートフェスをやって移住者を増やしているという実績があります。
来訪者を惹きつけるコンテンツを作り、つながりも創ることがこれから大事ではないかと。